「Kaizen Platformのエンジニアってすごい人しかいないんですよね?」 社外勉強会や面接の際によくいただく質問です。 大変ありがたい印象ではあるのですが、経験豊富なシニアエンジニアだけでなく、20代のメンバーも活躍しているので、実はみなさんが抱かれているイメージとはギャップがあるかもしれません。
「それって本当なの?(疑いの目)」 というみなさんの声が聞こえてきそうな…。
そこで今回は、昨年入社した2名のメンバーに「Kaizen Platformでの日常」を率直に聞いてみました。
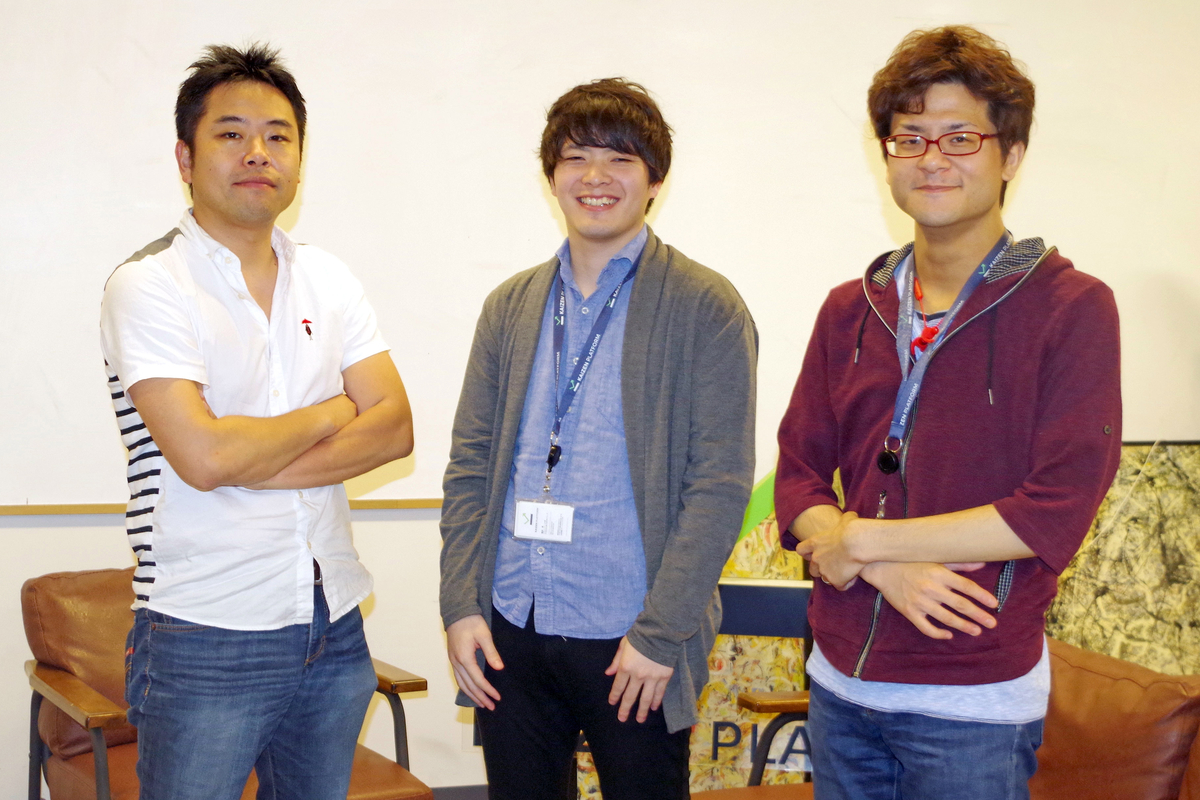
【インタビュイー】


【インタビュアー】

入社前、Kaizen Platformに抱いていた印象は?
徳田(とっくん):元々、Mediumで開発者Blogをやっている頃から読んでいたので、なんとなく技術的にすごい人がいる会社だなという印象がありました。あとは ryopekoさん が入社していることも知っていたので、そういうレベルの人たちが集まっている会社だという認識でした。レベルが高いと思っていたので、正直入社できるとも思っていなかったですね。
渡部:すごい人たちがいる場所で、自分が入社する会社というイメージではなかったということかな?
徳田:そうですね。僕のブログを見た人事から「CTOと話しませんか?」と連絡がきて面談したのをきっかけに入社しました。5−10年後に目指したい会社だなぁくらいの存在だったので、自分で直近応募するイメージはなかったです。連絡がなければこのタイミングで入社していないと思います。
木暮(木暮くん):僕は正直、とっくんほど Kaizen のことを知らなかったです。社長の sudokenさんのことは記事などを読んで知っていましたが、やっている事業やどんなチームなのかは知りませんでした。
渡部:ほとんど知らない会社にどういうきっかけで応募してくれたの?
木暮:前職を選んだ際に「社長がどんな人か」というのを大事にしていて、今回の転職でも社長軸で会社を探していました。Kaizen は「社長に魅力がありそうだし、どんなことをしている会社なのか話を聞きに行こう!」くらいの気持ちでHPから応募した記憶があります。
渡部:とっくんとは全然違う視点で当社のことを知ってくれたわけですね。「すごいエンジニア集団そう」みたいなイメージは全然持っていなかったということ?
木暮:はい。知り合いもいなかったので、あらかじめどんなエンジニアにいるのかは知りませんでしたね。
渡部:そんなよくわからない会社にどうして入社しようと思ってくれたの?
木暮:技術的に自分のメンターになってくれそうな人がいる環境に転職したいと思っていたのですが、応募時はKaizenがマッチするとは思っていませんでした。というのも、スタートアップやベンチャー規模でそういった環境があるわけないと思っていて、メガベンチャーを中心に受けていました。なので、自分の要件を満たす環境が Kaizen にないだろうなぁと思って期待していなかったのですが(笑)、選考で複数のエンジニアやCTOとプロダクトやチームメンバーの話をして、Kaizen なら教えてくれる=学べる環境があると思い、入社に至りました。
渡部:スタートアップとかベンチャーのイメージが変わったんですね。
木暮:そうですね。小規模な会社だと、フルスタックでとにかくプロダクト開発できる人だけを求めている勝手な印象がありましたが、技術を突き詰めている人がいるベンチャーもKaizen のようにあるんだなぁと。
入社してみてどうですか?
徳田:エンジアリングにおいてすごい人が集まっているというのはイメージ通りでした。いい意味でのギャップは、経験豊富なエンジニアでもわからないことは積極的に質問して、お互い教えあいながら協力しているのが当たり前な環境にはびっくりしました。
渡部:具体的によい刺激を受けたエピソードは何かある?
徳田:Chat Opsなど開発工程の自動化にはびっくりしました。デプロイをSlackでコマンドをうったら反映されるとか、GitHubのリリースブランチが定期で自動作成されたりとか。あとは、前職ではテストもあまりやっていなかったのですが、Kaizen ではテストもきっちりやるのでそういうところはすごい勉強になっています。

渡部:なるほど。少人数ながらもちゃんとした開発体制を整えているところは今までと違う環境で刺激があったんだね。慣れてくるとテストせずにデプロイとか怖くない?(笑)
徳田:そうですね(笑)プロダクト開発を一段上の視点でできるようになった感覚はあります。社外勉強会の記事で Kaizen の開発環境が整備されているのは知っていましたが、実際体験してみると、裏でいろんなものが動いていることを体験できて勉強になっています。
渡部:みんなで教えあう環境、というのは前職ではそこまでなかったのかな?
徳田:前職では、勤続年数の長い方数名に困ったことがあれば聞くという流れがあり、複数人で議論して解決する風土ではなかったです。
渡部:同じ会社の仲間なので、みんなで議論したり、わからないことを聞いたりするのは普通に思えるけど、意外に当たり前のことをやっている環境ってのは少ないのかもしれないですね。
徳田:たしかに、そうですね。入社して間もない頃は多少躊躇もありましたが、エンジニアみんなが得意分野以外のわからないことはカジュアルに聞いているし、それに対して「こんなのもわからないの?」という変なプレッシャーもないのを見ていて、自然に自分も質問して解決していくスタイルになりました。
渡部:木暮くんは何かある?
木暮:一定人数の会社規模で、特に働き方に関しては性善説運用でうまく回っているところに驚きました。自分が働きやすいと思う環境は会社に求めるのではなく、自分で作る、もしくは突き詰めると独立しないといけないと考えていましたが、入社直後の慣れない時期を除くと主体的に考えなくてもすで働きやすい環境があったのは意外でした。
渡部:たとえばどんな時にそう感じたの?
木暮:リモートワークをする上で、よりよくするためにみんなで常に努力しているところとかですかね。たとえば、リモートだとちょっとサボっちゃおうとか自分のいいように解釈する人とかがいると性善説運用が破綻してしまう思うのですが、そういう人がいないです。
渡部:みんながどんな風に努力していると感じる?
木暮:前提として、仕事に対するベースの価値観があっている人たちでチームが構成されているからこそ、性善説運用できている気がします。その上で、リモートワークを例にあげれば、各自が個人の利益ではなく、チームの働きやすさに真摯に向き合っているので、余計なルールはあんまり作らずに運用できていると思います。しかも中長期的に改善しながら運用する努力を続けているのも特徴で、形だけの制度ではなく、ちゃんと利用される制度= Kaizen の文化になっているところがいいなぁと。

渡部:信頼できない人がいないこととメンバー1人ひとりの働きやすさに対する努力があっての今の環境が成り立ってるということなのかな?
木暮:はい。強烈なリーダーシップによって同じ方向を向いているというよりは、全員で同じ方向を向いて仕事しようと各々が努力をしている感じです。自分にとっての働きやすさを追求するなら会社単位ではコストが高いと思っていたので、いつか起業してそういう場をつくることが最適解だと考えていましたが、会社へのバリューもだしつつ、働きやすさも追求できる会社があるかもしれないと思えたのは学びでした。
渡部:どうしてそれができてるんだろうなぁ。環境もプロダクトも両方みんなでつくっていくことに共感してくれる方に入社してもらっているのは1つ影響しているかも。
徳田:それはあると思います。
渡部:なるほど。そういう環境だったから活躍しやすかった?
木暮:そう思います。とっくんが言っていたように、技術的に自分よりできる人がわからないところを聞いていたりするのを見て、敷居が低くなって、日常のコミュニケーション全般で心理的安全性が高い環境だなと入社半年くらいでわかりました。
渡部:誰かに「聞いていいよ!」とか何かしらのイベントがあって背中を押されたわけではなく、日頃のあれやこれやをみて自然に大丈夫そうだなって感じたんだね。
木暮:はい。それがリモートワークをしている人が多くても、すごいエンジニアがいるなぁと思っても、安心して頼れる感じがしました。
渡部:実際に仕事をしてみて本当にすごいエンジニアがいるなぁとは思ったみたいだけど、彼らのすごさはどういうところで感じた?
木暮:ドキュメント化能力の高さは特に今までいた環境とは違いますね。たとえば、パッとつくったDesign Doc(設計仕様書)が内容に抜け漏れがほぼなく、全体を見渡して必要最小限のアウトプットがなされているところをみるケースが多く、そのレベルでドキュメントをつくれる人が多いと感じています。純粋に技術を知っているだけではなく、想定力が強い。
徳田:僕はレビューですね。自分が知らない技術やわかっていないことに対して、瞬時にイメージがつきやすい状態をつくってくれるのですごいと思います。しかも複数人がそういう指導をしてくれるので、いろんな観点からの知識を得ることができます。

渡部:Design Docとレビューなどの仕事をしていると自然と目に触れる他のエンジニアのアウトプットからすごさを感じるってことなんだね。
木暮:それがこの規模感のベンチャーでしっかりしていて、スピード感も維持できているのはすごいと思いますね。
徳田:たとえば、テストは「プロダクティビティをあげるためにテストをかく」ので不必要なテストは書いていなかったりするので、変に原理主義になっていないところもすごいと思います。
渡部:たしかに「このテスト無駄じゃない?」とか普通にエンジニアで議論してるし、カバレッジをあげることが目的化せず、あくまで「プロダクティビティをあげるためにどうしたらいいか」の視点をもって取り組んでいるかもしれないね。
入社してから1年間、どんな印象だったかをお二人にお話してもらいました。 後編(7月3日公開予定)ではKaizen Platformにおける課題感や、今後目指したい事について語ってもらいます。